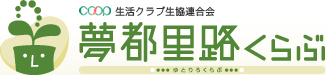取材記No.20「養殖こんぶの製品製造体験3日間(重茂漁業協同組合)」同行記(2025.5.21-22)
岩手県宮古市の重茂漁協といえば、肉厚わかめや昆布、せっけん運動など、関心がある組合員が多数いる生産者です。
今回、夢都里路くらぶが始まってから初めての漁業での企画化となりましたので、企画に同行させていただきました。

漁業での援農も、夢都里路くらぶが始まった当時から、方針に入れていましたが、なかなか企画化がかなわなかったのは、漁業特有の事情があります。
農業でも天候によって作物の生育が遅れたり、当日の作業が変更になることはありますが、漁業に関しては、日程を設定しても、時化となれば数日漁に出られないこともよくあり、事前に予定を組むのが難しいこと。また、船に乗っての作業は危険を伴う為、沿岸の作業に限られること。作業場となる沿岸に近い場所に宿泊先がなければ、早朝からの作業に対応できないことなど、多くの課題があります。
今回企画が可能になったのは、その全てをクリアできる条件が整ったからです。
一番は、漁港の近くで漁業体験の受け入れなども行っている民泊施設ができ、早朝からの作業などにも協力していただけるようになったこと。また、メインの作業は陸上でできる昆布の仕分け作業で、雨天時でも選別作業ができる為、時化に大きく関わらない為です。

今回の作業は、朝5時から開始します。
地元の漁家さんは、シーズン中は0時に出航し養殖こんぶを収穫、3時頃からボイル・冷却・選別の作業を行います。
1度に収穫する量は約1トン。この量を朝8時の出荷までに、全て作業を終える必要があります。
水揚げ後、90度に熱した海水でボイルし、茹で上がると今度は13度の海水でしっかり冷却。この作業で色と鮮度を保ち、水分蒸発を防いで保存性を高めます。

その後、選別作業を行います。
病気で模様が出たものや、腐って変色したもの、異物を除去します。異物の多くは「ヒラハコケムシ」という海産小動物で、昨年は海水温の上昇が原因でこのヒラハコケムシが急増し、選別作業にかなりの時間を要したそうです。
今年は海水温が例年並みだった為被害は比較的少なかったものの、それでも除去作業は2時間近く行いました。


朝の出荷を終えて、朝食をいただいてから、今度は塩蔵こんぶの選別作業へ。
ボイル・冷却した昆布は、そのまま出荷する場合と、漁家で塩蔵まで行ってから出荷する場合があり、今回は塩蔵こんぶの出荷前の選別を行いました。
参加者は2つの漁家さんに分かれ、作業を行いました。作業のやり方は漁家さんによって違いがあるそうですが、家族数人で昼頃までこの作業を行うところが多いそうです。

重茂地域も高齢化や後継者問題を抱えています。
漁業は農業以上に親子での技術継承で受け継いできており、新規参入が他より難しい業種だそうです。
だからこそ、この夢都里路くらぶのように、産地を知ってもらうこと、利用につなげてもらうことが大きな力になります。
今回の企画化を一度きりで終わらせず、長く継続できる企画にし、一人でも多くの組合員が産地を体感できる機会としたいです。