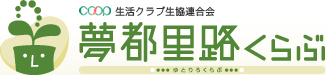No.549 原発事故で翻弄された阿武隈の再生を願う活動に頭が下がる思い 「福島県阿武隈の里をウルシの里へ!下草刈り(毎月開催!!)」
生産者名: 酒井産業(株)
日付:①2025年5月14日(水)~5月16日(金)
②2025年6月11日(水)~6月13日(金)
③2025年7月16日(水)~7月18日(金)
④2025年8月13日(水)~8月15日(金)
⑤2025年9月17日(水)~9月19日(金)
昨春と今春に植えられたウルシの苗木の周りに生い茂る草を、鎌で刈り払う作業です。
まだ5月なのに、苗木が見えないほど草は伸び、乗車型草刈り機の「まさお」(草刈正雄にちなんだ商品名)が間違って苗木まで切り倒さないよう、苗木の周囲30〜40センチを刈り上げます。
初日は約1ヘクタール、2日目は5反(約5000平方メートル)の草を刈り、1000本を超す苗木がきれいに姿を見せると、「やったー」という達成感がありました。
作業した2日間、最高気温は22.7度で、風もあって快適でしたが、7月や8月は大変だと思います。「生活と自治」の元編集長で「阿武隈牛の背ウルシぷろじぇくと」共同代表の内野祐さん(73)は昨年、2度、熱中症でダウンしたと話していました。
ウルシは日当たりのいい所を好み、最低5年は下草刈りが必要だそうです。多くの人の手伝いが必要です。
阿武隈の里山は、コナラやクヌギなどシイタケ栽培に使われる原木の国内有数の産地でした。福島第1原発の事故で、放射性物質が降り、原木も国の基準(1キロ当たり50ベクレル以下)を超えるセシウム137で汚染されて、出荷制限が続いています。
里山は人の手が入らなくなり、過疎化、高齢化で田畑の耕作放棄地も増えました。荒廃に向かう里山、里地の再生を目指して、「生活と自治」の「産地百景」でおなじみの写真家・田嶋雅己さん(71)や内野さんが中心になって2023年に始めたのが「阿武隈牛の背ウルシぷろじぇくと」です。
ウルシが高さ10〜15メートルに成長し、樹液が採れるようになるまで15年。先の長い取り組みですが、何万本ものウルシが育てば、そこに樹液の掻き手、木地師、塗師ら職人や芸術家が集まり、新しい産業や文化もきっと生まれる。そう信じての活動です。
イノシシ、遅霜などさまざまな困難に直面しながらも、原発事故で翻弄された阿武隈の再生を願う、その思いの高さに頭が下がりました
(5月参加 埼玉、60代男性)
ウルシの幼木の周囲の雑草を鎌で刈り取る作業
その後の草刈りは漆プロジェクトの方たちが常用草刈り機などで綺麗にしてくれました。
原発事故に起因する「漆プロジェクト」ができた理由や経緯を詳しく説明してもらって、作業への大きなモチベーションになった。
食泊地を検討いただけたら(コストの問題)もう少し長く作業してもいいと思った
でも宿は快適でした
(7月参加 兵庫、70代男性)
耕作放棄地を活用して、漆の原木を植え、15年の年月をかけて、育てるプロジェクト。漆の木の下草取り作業を行いました。
1日目:参加メンバーとの懇親会。今回は太陽ネットワーク物流のメンバーも参加し、交流会を行いました。
2日目:漆の木の下草刈り作業。生活クラブ福島の組合員、職員の方4名の参加があり、一緒に作業をしました。暑い中、草取り作業は大変です。昼ご飯の準備を福島の組合員が用意してくれました。カレー、野菜など。昨年、参加したときに、福島の組合員が参加しました。その方が福島の組合員に声をかけてくれて、作業に協力してくれました。これからも継続して参加してくれると良いと思います。午後からは放射線の影響を受け、土地の土入れ替え作業した圃場の草取り作業、土のならし作業を行い、2日目の作業は終わりました。
3日目:3年前に苗を植えた圃場の草取り作業でした。漆の木の下草刈り。月に一度の草刈りをしている圃場でしたが、草は伸びるもので、周りは草刈り機で除草し、木の下の作業を行いました。3日目は夢都里路くらぶの参加者3人と生産者での作業でしたが、決められた場所の草取り作業が早めに終わり、生産者と企画者と意見交換を行いました。福島の復興はまだまだこれからであることを感じました。これからも応援していきたいと思います。ありがとうございました。
福島の組合員と交流ができたこと。圃場がきれいになったことが良かったです。
(7月参加 神奈川、60代女性)
整然と植えられたウルシの苗の、周りの草を鎌で刈る作業をやりましたが、苗の周りをぐるっとまわるように動きながら刈っていたら、全く違う方向に進んでいました。しばらく気づかずに他の人が既に刈って根元に寄せていた草をまたちらかしたり、さらにその外側を刈ったりしていました。
また、「土寄せ」という作業をやりましたが、道具を使い慣れてないので、こちらはすぐにばててしまいました。しかし、山の中にクロモジを植栽した現場を見に行ったことでリフレッシュできました。
2日目も苗の根元の草を刈りましたが、少し学習して初日より効率的にできたと思います。ウルシかぶれ対策に厚手のゴム手袋を使用していたことで、(うるしを触った手で)不用意に顔など触らないよう意識できました。暑さにも2日目は少し慣れたようにも思います。
良かったこと…人との出会い 発起人の皆さんはもちろん、今回一緒に作業に参加した方々といろんな話をしたり、聞いたりできたことが1番の収穫と感じました。思いがけず生活クラブ福島の組合員の方たちにお昼を用意していただいたのは大変な負担だったと思うけれど、とてもありがたかったし、もっといろんな話ができたら良かったな、、と思いました。
・参加者のために臨機応変に対応していただいたこと(最終日の着替え時間と場所確保のみならず、お風呂まで使わせていただけた)
・ウルシやクロモジの話を聞けたこと
植えてからウルシが取れるまでに15年、そこがやっと産業としてのスタート地点になるという気の長い話。目の前の農作業をこなしながら並行して産業としてスタートするための準備をしていかないといけない、大変なプロジェクトだと思います
改善が必要なのは自分の悪かったところだけです。
・2日目、とても暑くなるとの予報だったので、朝コンビニで昼食を購入してから現場に来るよう言われていたのに、お昼になってから買いに行きたい、と現場についてから要望をしたことで、おそらく予定が変わり、大変ご迷惑をおかけしました。考えが甘かったです。とにかくお店なんてない。次に暑い中コンビニで昼食を購入する時は、事前に保冷バッグを持たせていただけるとありがたいと思います。
面倒だからもうこなくていい、と言われませんように。
・1日目の作業の畑が、除染土の仮置き場にされていたこと、その後天地返しなどして今に至ることを聞き、ハッとしました。震災・原発事故から受けた影響は福島でも地域により様々です。この地域のことをもう少し頭に入れておけば良かったかなと思いました。
(7月参加 神奈川、60代女性)
漆の木の下草刈り、3ヶ所
福島の方が手伝いに来てくださり、大勢でしたので、はかどり楽しく出来ました。
休憩の水、お昼も、たくさんの差し入れで、しっかり食べれて良かったです。
お世話になり、ありがとうございました。
(8月参加 神奈川、60代女性)
田んぼ跡地や牧草跡地に植栽されたウルシの木の周りの草を鎌で刈って根元にかぶせる作業
草刈り機で刈れない部分(電気柵の周り)の草刈り
消費材に直接かかわらない異色の企画だが、背景が壮大で、これからも関わっていきたいと思える意味のある企画だった。また、PJメンバーに福島の組合員も入っており、夢都里路の作業日に一緒に参加してくれた。とても心強かった。
PJ立ち上げメンバーの方は『生活と自治』の編集者であった経歴があったり、『失われた春』(11月に神奈川のオルタ館で上映予定)の映画監督だったり、地元の林業の方だったりということで、ちょうど私の興味のあるところでもあり、予期せぬ出会いがあったのも財産となった。
泊まった日の夜に『失われた春』が参加者で見られるといいなと思った。
(8月参加 神奈川、50代女性)
東京電力福島第1原発事故で大きな被害を受けた福島県の阿武隈山地の再生を願って、耕作放棄地に植えられたウルシ、クロモジ、コウゾの下草刈り作業です。前回は手鎌で刈り取りましたが、今回初めて刈払機を使った除草もしました。
5月以来、4カ月ぶりの参加でしたが、春は背の高い雑草に埋もれていたのに、ひと夏で50センチ以上伸びた木もあって、その成長に驚きました。夢都里路くらぶの参加者は私ひとりでしたが、生活クラブ福島から3人、生活クラブと関係が深い茨城の生産者・丸エビ倶楽部から2人、それに「浄法寺漆」の岩手県二戸市や「会津漆」の福島県金山町のウルシ掻き職人も加わって、総勢12人。3年目を迎えた「阿武隈牛の背ウルシぷろじえくと」が一歩ずつ広がっていることに感動しました。
プロジェクトは、ウルシはまったく素人の写真家の田嶋雅己さんと編集者の内野祐さんに、木曽漆器を扱う酒井産業の酒井慶太郎さんが加わって、3人で始まりました。初年度の2023年はイノシシと遅霜で、ウルシはほぼ全滅。年に2000本以上の植栽を目指していますが、苗木が1本1000円(2000本で200万円)もすることから、今年はろうで覆われている直径6〜8ミリほどのウルシの実を熱湯で脱ろう処理して発芽させる実生(みしょう)を試みました。発芽率は10%と言われているそうですが、4万粒試して発芽したのは300粒。発芽率は1%以下(0.75%)だったそうです。壁にぶつかりながら、試行錯誤を重ねています。
ウルシが成長し、樹液を採取できるようになるまで10〜15年かかります。先は長く、多くの方の手助けが必要です。
田嶋さんと内野さんが困難に出会って、失意の底にあるときに向かうというウルシの木を見に行きました。協力者の「あぶくま山の暮らし研究所」の青木一則さんが2022年に植えたウルシです。
元は田んぼで水はけが悪く、ウルシの植栽地としては条件が良くないそうですが、5メートル近い高さに育っていました。田嶋さんと内野にとって「希望」の象徴で、一緒に見上げているとジーンときました。
(9月参加 埼玉、60代男性)